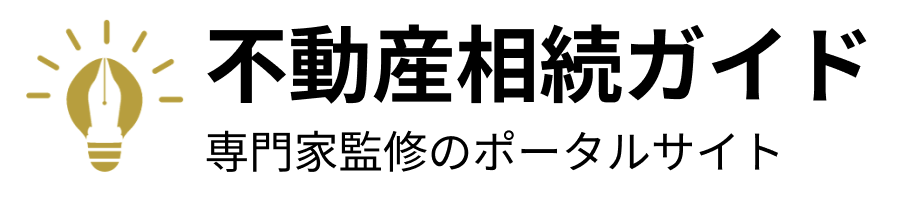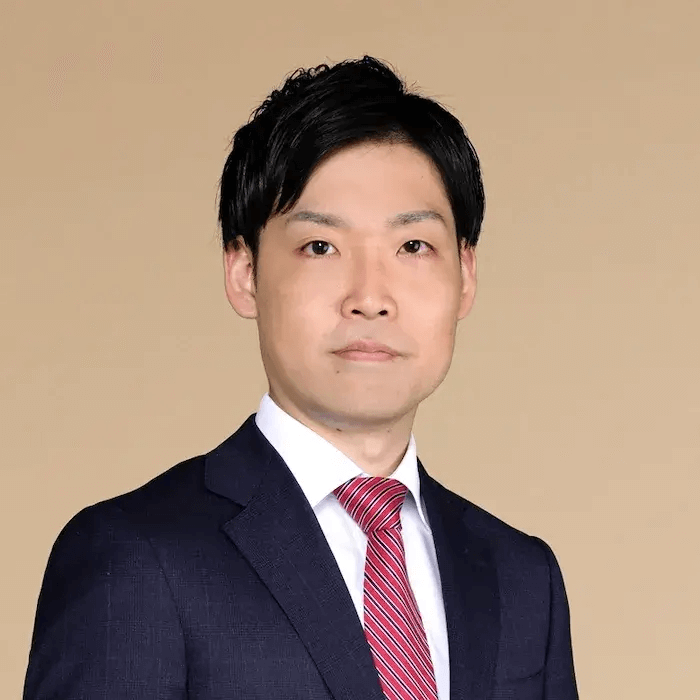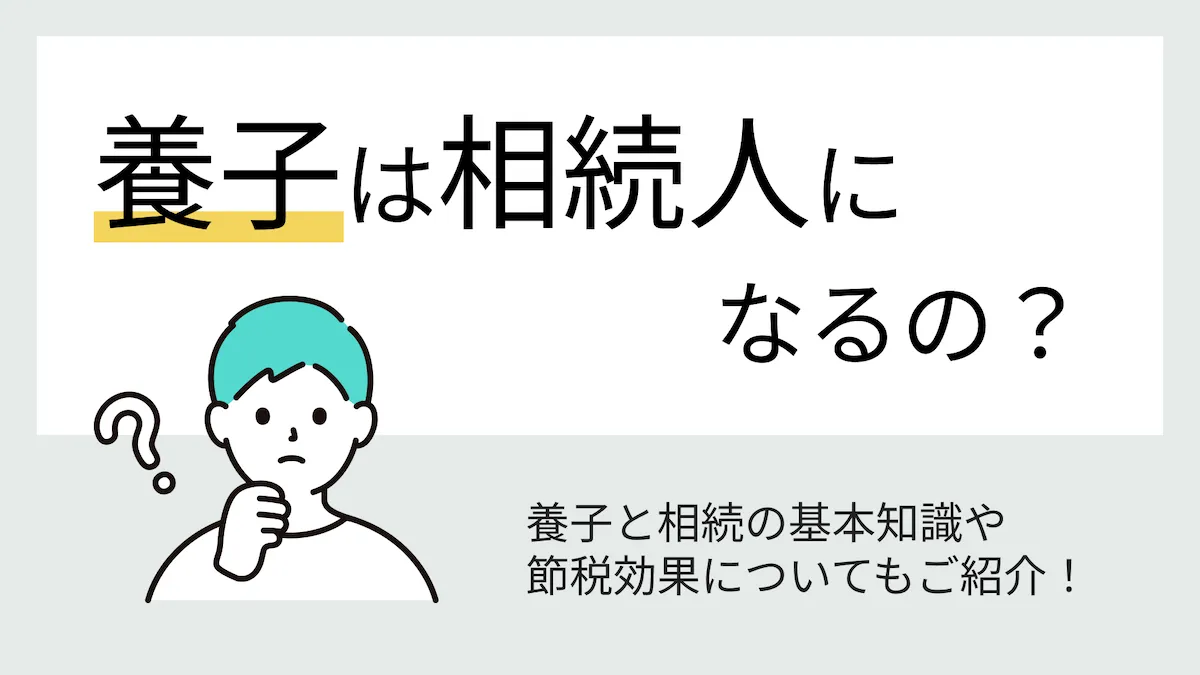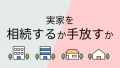「養子は相続人になるのか?」「養子がいると相続税を軽減できるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、養子縁組と相続の基本的な仕組みから、実際の事例、税務上のメリット・デメリットまでを分かりやすく解説します。
1. 養子縁組とは?
養子縁組とは、法律上の親子関係を新たに築く制度であり、実の親子と同等の権利義務が発生します。相続や税務対策などを目的に活用されるケースも見受けられます。養子縁組には大きく2つの方法があります。
(1)方法①|普通養子縁組
普通養子縁組は、実親との親子関係を維持したまま、新たに養親との親子関係を築く制度です。未成年者だけでなく、成人を養子とする養子縁組も可能で、家庭裁判所の許可は原則として不要です。
例えば、孫を養子にするようなケースや、いわゆる婿養子となるケースで利用されることが多い方法です。
普通養子縁組でも、養子は法定相続人としての権利を持ち、相続順位も実子と同様に扱われます。
(2)方法②|特別養子縁組
特別養子縁組は、原則として15歳未満の子どもを対象とし、実親との親子関係を完全に終了させる制度です。
普通養子縁組と比べて強い効果が生じる方法であるため、家庭裁判所の決定が必要であり、慎重な手続きが求められます。
特別養子となった子どもは、養親とのみ親子関係が成立するため、実親との関係では相続権を一切失います。特別養子縁組は、児童の福祉を目的としたもので、通常、相続税対策には用いられません。
2. 養子は実子と同じく「法定相続人」になる
養子縁組が成立すると、養子は実子と同等の法定相続人になります。つまり、民法上の「子」として、相続の際には第一順位で遺産を受け取る権利を持ちます。
これは重要な点で、養子が相続人としてカウントされることで、相続税の基礎控除額が増えるなどのメリットが発生します。
他方で、複数の子がいる場合は、養子も含めて遺産を均等に分ける形となるため、事前の対策がないとトラブルの原因にもなり得ます。
3. 養子縁組の実例
養子縁組は、単に子どもがいない家庭だけでなく、多様な家族構成の中で活用されています。ここでは、養子縁組が利用される代表的なケースをご紹介します。
(1)子供の配偶者と養子縁組するケース
子供の配偶者、つまり「娘婿」や「嫁」と養子縁組をするケースです。このケースは、家業の承継や財産管理を円滑に行うためにもよく用いられます。
また、被相続人の子の配偶者が長年介護や家業の支援をしていた場合、その貢献を相続に反映させる意味を込めて、養子縁組がなされるケースもあります。
このケースでは、本来相続人にはならない“被相続人の子の配偶者”が養子となることで、法定相続人として正式に遺産を受け取ることができるようになります。
ただし、他の相続人とのバランスを考慮しないと、遺産分割で争いになることもあるため、注意が必要です。
(2)孫と養子縁組するケース
孫との養子縁組は、相続税の軽減策として利用されることがあります。
例えば、実子がいる場合にも、養子縁組をすることで法定相続人の頭数を増やし、相続税の基礎控除額を増やすことも理屈上は可能です。
ただし、養子にできる人数には税務上の制限がある点には注意が必要です。具体的には、
- 実子がいる場合には、養子は一人まで
- 実子がいない場合には、養子は二人まで
と決まっています。
(3)再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組するケース
再婚相手の子ども、いわゆる「連れ子」との養子縁組も一般的です。縁組を行うことで、血縁関係がなくても法的に親子となり、相続権を持つことになります。
4. 養子縁組で相続税対策を行うメリット
養子縁組をすると、結果的に支払う相続税が軽減されることがあります。ここでは、具体的な3つの税務上のメリットを解説します。
(1)相続税の基礎控除額が上がる
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、養子を迎えることで法定相続人の数が増え、その分控除額が増加します。
例えば、子どもが1人しかいない家庭で、孫を養子にすると、控除額が「3,000万円+600万円×2=4,200万円」となり、課税対象額を抑えることができます。
ただし、控除の対象となる養子の数には上限があるため、無制限に増やせるわけではない点に注意が必要です。民法上は養子の数に制限はありませんが、税務上は、次のような上限があります。
- 実子がいる場合には、養子は一人まで
- 実子がいない場合には、養子は二人まで
養子縁組をたくさんすれば相続税を無限に下げられる、というわけではありません。
なお、子供がいない状況で養子縁組をすると法定相続人の数が減ってしまう場合がありますのでご注意ください。
(2)生命保険金の非課税枠が増える
生命保険金(死亡保険金)の非課税枠も同様に、法定相続人の数に基づいて計算されます。具体的には、「500万円×法定相続人の数」で計算します。
養子縁組により法定相続人が増えれば、この非課税枠も拡大します。
例えば、法定相続人が2人なら1,000万円まで非課税ですが、養子が加わって3人になれば1,500万円まで非課税となります。
(3)死亡退職金の非課税枠が増える
被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは、相続税の課税対象になります。
ただし、相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
したがって、養子縁組によって相続人が増えれば、ここでも節税効果が期待できます。特に、退職金が多額になるケースでは、養子縁組による相続人の増加が有利に働きます。
5. 養子縁組で相続税対策を行う際の注意点
養子縁組は相続税対策として効果的な手段である一方で、注意すべき落とし穴もいくつか存在します。場合によっては逆効果になることもあるため、活用の際には慎重な検討が必要です。
(1)家族構成によっては相続税対策にならない可能性
養子縁組が相続税対策にならない可能性もあります。例えば、被相続人に配偶者と両親がいる場合、養子縁組を行うことで法定相続人が減り、結果的に基礎控除額も減ってしまうことがあります。
(2)遺産分割協議で揉めるリスクが高まる
養子が増えることで、当然ながら相続人の数も増加します。その結果、遺産分割協議が複雑化し、話し合いがまとまらず揉めごとに発展するケースも少なくありません。
特に、もともと実子がいる家庭で新たに養子を迎えた場合、実子から「相続分が減る」として不満が出ることもあります。
円満な相続を目指すなら、養子縁組をする意図を生前に家族にきちんと説明し、可能であれば書遺言の作成まで行うのが理想的です。
(3)相続税額が2割加算されることがある
孫を養子とする場合、相続税が2割加算となります。養子縁組をすると、民法上では実子と同じ一親等の血族(法定血族)となります。しかし、孫を養子とした場合、被相続人の子の相続税を1回免れることになるため、2割加算の対象となります。
つまり、形式的に相続人の数を増やすためだけに縁組を行ったとしても、結果として課税額が増えてしまうケースも考えられるのです。
(4)相続税対策のための養子縁組は否認されることもある
こちらはとても重要なポイントで、税務署は、相続税の過度な軽減を目的とした「形式的な養子縁組」を否認する可能性があります。
実態が伴わない場合、たとえば相続直前に縁組を行っていて、縁組後も親子関係としての実体が見られないなどのケースでは、租税回避とみなされるリスクがあります。
養子縁組は法律行為である以上、その真意や生活実態が問われます。税務署とのトラブルを避けるには、縁組後も定期的な交流があることや、生活面での関係が構築されていることが重要です。
(5)法定相続人が増える人数には制限がある
養子を増やすことで相続人の数を増やし、控除額や非課税枠を広げることができますが、税務上は無制限ではありません。
繰り返しになりますが、具体的には、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除等の対象としてカウントされます。
6. まとめ|養子の相続で困ったら弁護士に相談を
養子縁組は、法律的にも税務的にも非常に強力な相続対策の手段です。普通養子縁組であれば実子と同等の相続権が得られ、結果として相続税の負担軽減にもつながります。ただし、家族関係や財産状況によっては、思わぬトラブルや税務リスクを招くこともあります。
これから養子縁組をすることを検討している方も、すでに養子縁組をしていて相続問題に直面している方も、困ったらできるだけ早いタイミングで弁護士等の専門家に相談するようにしてください。