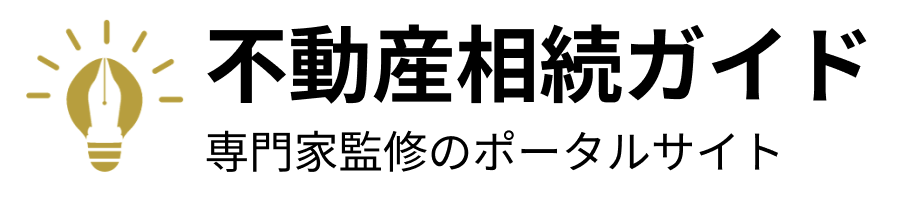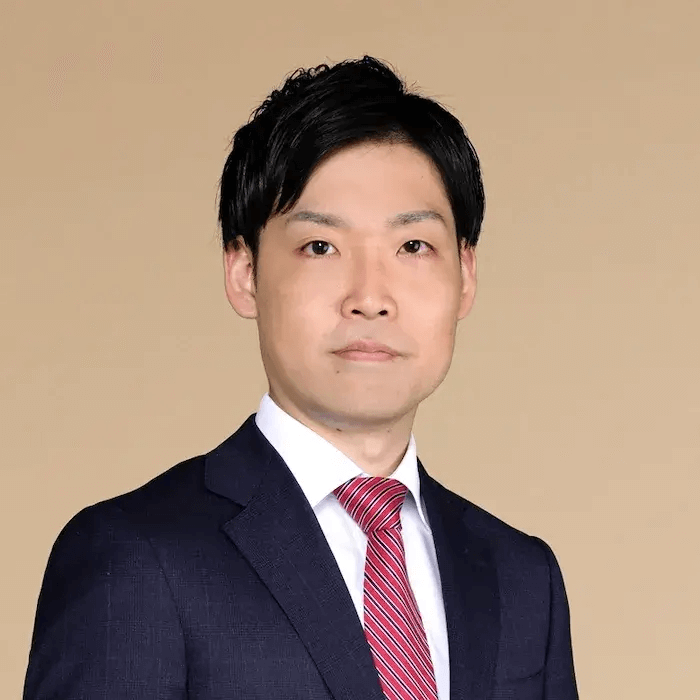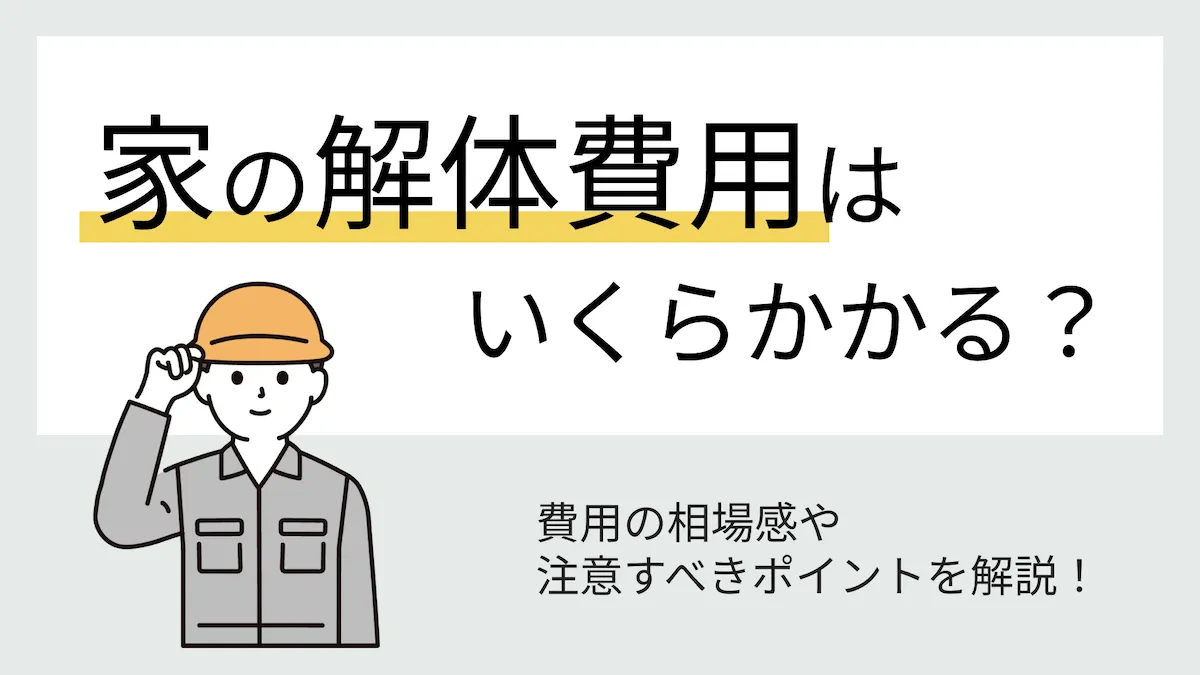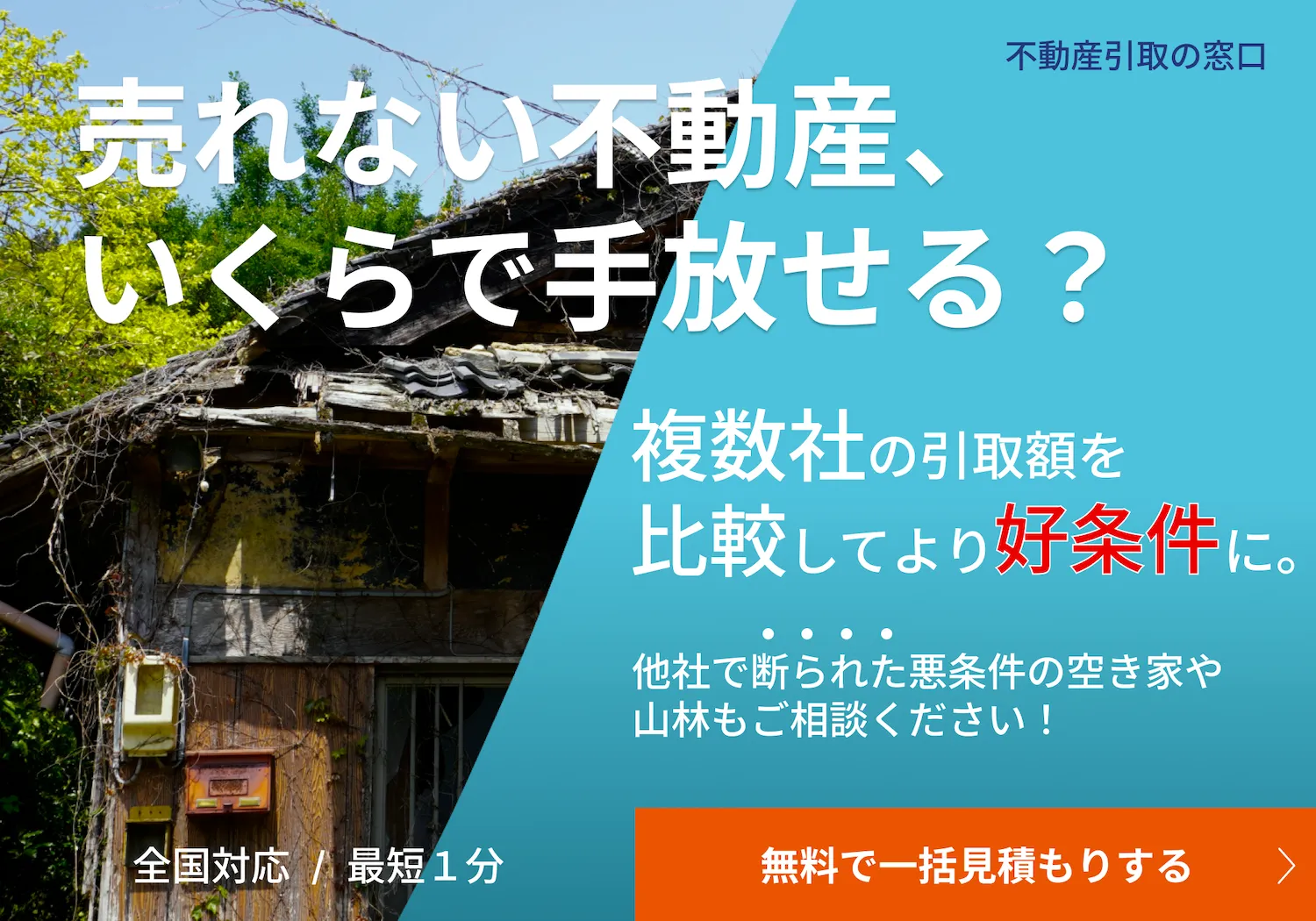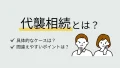空き家や老朽化した建物を所有していると、「家を解体したい」と考えることもあるでしょう。しかし、解体には費用や手続きが多く関係し、どこから始めればよいか迷う方も少なくありません。この記事では、家の解体費用の相場から必要な手続き、注意点までを詳しく解説します。
1. 家の解体費用の相場
家を解体する際にまず気になるのが「解体費用がいくらかかるのか」です。
建物の構造や立地、周辺状況によって金額は大きく異なりますが、ある程度の相場を把握しておくことで、適正価格で依頼する助けとなるでしょう。
目安として、一般的には100万円〜400万円程度の範囲で収まることが多いでしょう。
(1)一軒家の解体費用の相場
| 構造 | 解体費用の相場(1坪あたり) |
|---|---|
| 木造住宅の解体工事 | 3~5万円程度/坪 |
| 鉄骨造住宅の解体工事 | 5~7万円程度/坪 |
| RC住宅の解体工事 | 7~9万円程度/坪 |
一般的な木造住宅の解体費用は、1坪あたり3〜5万円程度が目安です。仮に30坪の家であれば、90万円〜150万円程度となります。
鉄骨造は1坪あたり5〜7万円、鉄筋コンクリート造(RC造)では1坪あたり7〜9万円と、構造が頑丈になるほど費用が高くなります。また、地域差や作業環境によっても金額は前後します。
(2)解体費用の変動要因は?
解体費用は単純な建物の大きさだけでなく、以下のようなさまざまな要因で変動します。
- 建物の構造(木造・鉄骨造・RC造など)
- 立地条件(道路幅、交通量、周辺環境)
- 作業スペースの有無
- 地下室や基礎の有無
- 築年数や老朽具合
例えば、狭小地で重機が入れない場合や、人力による解体が必要な場合は、作業時間や人件費が増えるため費用が高くなる傾向にあります。
(3)解体工事以外にかかる費用も
また、解体そのものかかる解体工事費用以外にも、次のような費用が必要になる場合があります。
- 建物滅失登記の費用(数万円程度)
- 廃材処理費用
- アスベスト調査・除去費用(10万円〜数十万円)
- 整地費用
- 養生シート設置費用
これらを含めると、総額で想定よりも大きな出費になる可能性があるため、初期段階で見積もり内容をしっかり確認することが大切です。
2. 家を解体するときの流れ
家の解体は、見積もりから工事終了まで複数のステップを踏んで進めていきます。スムーズに進めるためには、あらかじめ全体の流れを理解しておくことが重要です。
(1)解体費用の見積もりの取得
まずは複数の解体業者に見積もりを依頼します。建物の構造や立地、周辺の状況に基づいて概算費用が提示されます。
訪問見積もりを依頼すると、より正確な金額がわかります。業者によって費用やサービスの内容に差があるため、相見積もりは必須と考えましょう。
解体費用一括見積もり【無料】AD
「今すぐ解体するつもりはないけれど、解体するとなれば費用がいくらかかかるか気になる」という方は、無料で解体費用の一括見積もりを行える「解体無料見積ガイド」を利用してみましょう。
解体費用は、建物がある場所や構造、解体希望時期などによって費用が異なるため、まずは見積もりをとって、具体的な費用のイメージをもつことが重要です。
サイト利用者数10万人を突破している「解体無料見積ガイド」なら、あなたの解体工事に適任の解体業者を数社選別して見積もり可能!いきなり複数の業者から電話がかかってくることもありません。中には、「100万円以上安くなった」というケースも。解体を検討している方は、一度見積もりをしてみてはいかがでしょうか。
(2)依頼する業者の決定
見積もりを比較した上で、価格だけでなく実績や対応の丁寧さ、追加費用の有無、口コミなども確認して業者を選定します。建設業許可や産業廃棄物処理業の登録があるかもチェックポイントです。契約前には、契約書や見積書の内容をよく確認しましょう。
(3)事前準備
契約後、工事前に近隣住民への挨拶を行っても良いでしょう。騒音や振動が発生し、トラブルが発生する可能性がゼロではないからです。
また、ガス・電気・水道の停止手続きや、内部に残された家具・家電の処分なども済ませておく必要があります。
(4)解体工事
いよいよ解体工事が始まります。まずは足場の設置や養生シートの張り付けから始まり、重機による解体作業が行われます。
作業期間は建物の規模や状況によって異なりますが、数日〜2週間程度が一般的です。
(5)廃材処理
解体後に出る廃材は、種類ごとに適切に分別され、産業廃棄物として処理されます。処分費用は解体費用に含まれていることが多いですが、アスベストや特殊な廃材が含まれる場合は別途費用がかかることもあります。
(6)整地
解体が終わった後は、土地を平らに整える「整地」作業が行われます。これにより、売却や再建築の準備が整います。地中にコンクリート塊などが残っていると後の工事に支障が出ることもあるため、しっかりと整地されているか確認しましょう。
(7)建物滅失登記
最後に「建物滅失登記」を法務局に届け出ます。これは、解体によって建物が存在しなくなったことを登記簿上で反映させるための手続きです。
自分で申請することもできますが、司法書士に依頼する場合は2万円〜5万円程度の費用がかかります。
手続きが完了すれば、建物の登記簿は閉鎖され、建物の固定資産税がかからなくなります。
3. 家を解体する前に必要な届出等
解体工事を始める前に、法律で定められた届出が必要な場合があります。無届で工事を行うと罰則が科されることもあるため、事前の確認と準備が重要です。
例えば、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、延べ床面積80㎡を超える建物の解体には届出が必要です。届け出は工事着工の7日前までに行う必要があります。届出は原則として施主が行いますが、通常は解体業者が代行してくれることが多いでしょう。
また、道路使用許可や近隣への通知、ライフラインの停止手続きなど、各種届出や調整が必要になるケースもあります。地域によって異なるため、自治体窓口や業者に事前に確認することをおすすめします。
4. 解体期間は1〜2週間程度
一般的な木造住宅(30〜40坪)の解体にかかる期間は、約1週間〜2週間程度です。ただし、建物の構造や立地、天候などにより前後することがあります。
たとえば、鉄骨造やRC造の建物では工期が2週間以上に延びることもありますし、敷地が狭く重機が入りづらい場合は作業効率が落ち、時間がかかる傾向にあります。
また、アスベストの除去が必要な場合や地中埋設物の撤去が発生した場合なども工期が長くなります。
工期が延びるとそれに伴って費用もかさむことがあるため、あらかじめ業者と詳細なスケジュールを打ち合わせておくことが大切です。
5. 解体工事以外にかかる費用も確認
解体費用には工事そのものだけでなく、付帯するさまざまな費用が発生します。見積もりを確認する際は、これらが含まれているかどうかをしっかりチェックしましょう。
(1)付帯工事費
付帯工事とは、建物の解体に直接関係しないが必要となる作業のことを指します。たとえば、以下のようなものがあります。
- ブロック塀、フェンス、庭木、物置などの撤去
- 地中の浄化槽や井戸の埋戻し
- 車庫やカーポートの解体
これらは建物本体の解体とは別料金になることが多く、事前に業者と打ち合わせておく必要があります。
(2)アスベスト調査・工事
築年数の古い建物(概ね1990年以前に建てられた建物)には、アスベストが使用されている可能性があります。健康被害のリスクがあるため、事前に専門調査を行い、必要であれば除去作業が求められます。
調査費用は5万円〜10万円前後、除去工事には10万円〜数十万円かかるケースもあります。これらの費用も工事見積もりに含まれているか確認しましょう。
(3)その他諸経費
解体工事に伴って発生する諸経費も見落とせません。例えば次のようなものがります。
- 足場設置費
- 養生シート設置費
- 廃材の運搬費・処分費
- 役所への各種申請費用
- 近隣対策費
見積書に「一式」と記載されている場合は、詳細を業者に確認しましょう。
6. 解体費用や諸費用を抑える方法
解体工事には多額の費用がかかるため、少しでも費用を抑えたいと考える方も多いと思います。ここでは、費用を削減する具体的な方法をご紹介します。
(1)複数の業者から相見積もりを取る
解体業者によって提示する金額は異なります。費用を安く抑えたいのであれば、必ず複数社(できれば3社以上)に見積もりを依頼しましょう。費用だけでなく、対応の丁寧さや提案内容も比較することで、納得できる業者を選ぶことができます。
解体費用一括見積もり【無料】AD
「今すぐ解体するつもりはないけれど、解体するとなれば費用がいくらかかかるか気になる」という方は、無料で解体費用の一括見積もりを行える「解体無料見積ガイド」を利用してみましょう。
解体費用は、建物がある場所や構造、解体希望時期などによって費用が異なるため、まずは見積もりをとって、具体的な費用のイメージをもつことが重要です。
サイト利用者数10万人を突破している「解体無料見積ガイド」なら、あなたの解体工事に適任の解体業者を数社選別して見積もり可能!いきなり複数の業者から電話がかかってくることもありません。中には、「100万円以上安くなった」というケースも。解体を検討している方は、一度見積もりをしてみてはいかがでしょうか。
(2)補助金制度を利用する
自治体によっては、空き家の解体に対して補助金を支給しているところがあります。補助額は数十万円に及ぶ場合もあり、条件を満たせば大きな節約になります。募集期間や条件があるため、自治体のホームページ等で早めに確認することが重要です。
(3)工事時期を解体業者側の都合にあわせる
解体業者の閑散期(1〜2月、6月〜9月など)に依頼することで、割引を受けられることがあります。業者に「閑散期の割引などはありますか?」と聞いてみても良いでしょう。
(4)建物滅失登記の申請を自分で行う
建物滅失登記は、自分で申請することも可能です。戸籍謄本等の必要書類をそろえて法務局に提出することができれば、数千円の出費で済むでしょう。司法書士に依頼すると2〜5万円程度の費用(報酬)がかかるため、自力で行えば節約になります。
(5)「空き家解体ローン」を利用する
一括での支払いが難しい場合は、銀行などが提供する「空き家解体ローン」の利用を検討してみましょう。低金利で借りられるものもあり、家計の負担を軽減できます。
7. 家を解体する前に知っておきたいこと
家を解体することで発生する「意外なデメリット」も存在します。後悔しないためにも、以下の点に注意しておきましょう。
(1)家を解体して更地にすると固定資産税が上がることがある
建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が数分の1に軽減されているのが一般的です。しかし、建物を解体して更地にするとこの特例の適用がなくなり、税額が数倍に増加することがあります。解体後も土地を使わずに保有する場合は、税負担の増加に注意が必要です。
(2)家を解体して更地にすると再建築不可になることがある
再建築不可物件とは、現在は家が建っているものの、解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地のことです。
都市計画区域内では、再建築にあたって「接道義務」を満たしている必要があります。現存する家は建築当時の基準で建てられている場合も多く、いざ解体してしまうと再建築ができない「再建築不可物件」となる可能性があります。
解体前に建築士や不動産業者と相談し、再建築の可否を確認しておくことが重要です。
8. 家を解体せずに売却することも検討を
家の状態によっては、あえて解体せずに「古家付き土地」として売却するという選択肢もあります。買い手側が自分の希望に合わせてリフォームや建て替えを検討できるため、需要がある地域ではそのままの状態でも売れることがあります。
また、解体費用をかけずに済むため、手元にお金を残したい方や相続した家を早く処分したい方にとっても有効な方法です。素人判断では難しい点も多いため、不動産業者に相談して「解体して売るべきか」「現状で売れるか」を判断してもらいましょう。
9. まとめ
家の解体には、想像以上に多くの手続きと費用が伴います。費用相場や流れを理解した上で、信頼できる業者に依頼し、必要な届出や補助制度をしっかりと活用することが、後悔しない解体につながります。
また、解体後の税金や再建築の可否、売却の選択肢も含めて、総合的に判断することが重要です。本記事を参考に、あなたにとって最適な解体・活用方法を検討してみてください。