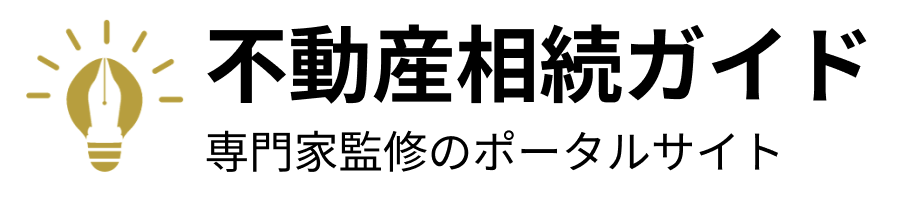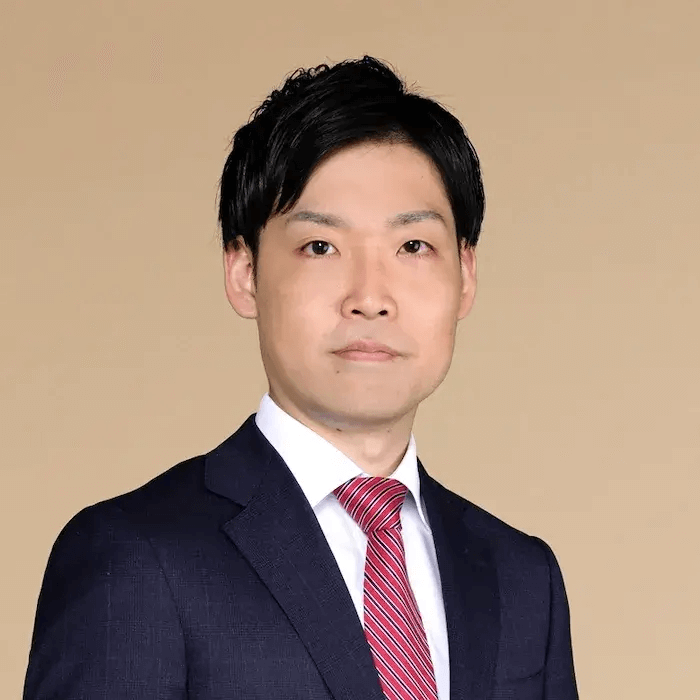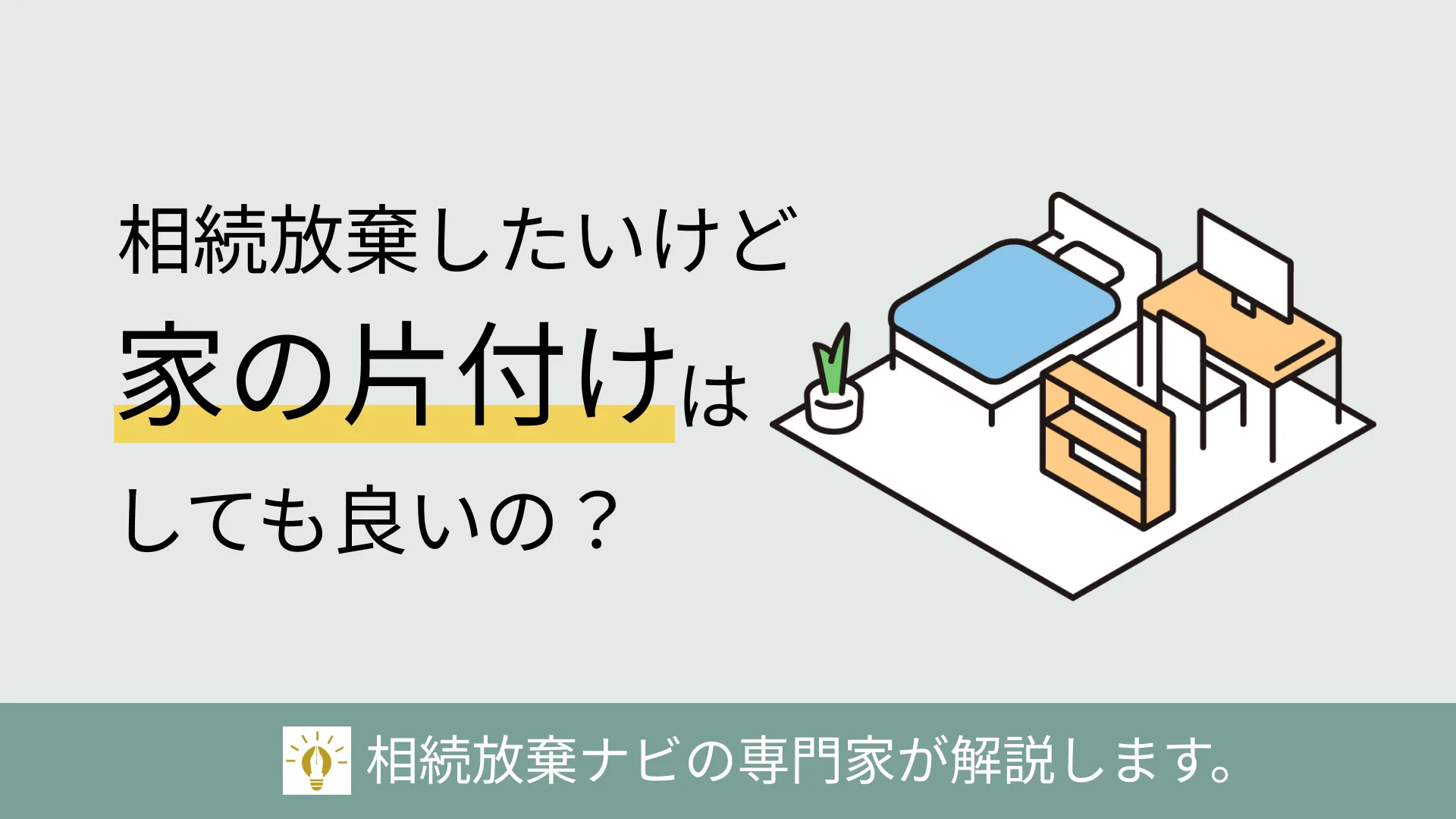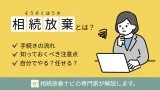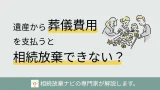これから相続放棄をする人も、すでに相続放棄をした人も、亡くなった方の家の片付けをするときは注意が必要です。片付けの内容によっては、相続放棄ができなくなったり、すでにした相続放棄の効力が否定されたりするリスクがあるためです。この記事では、具体的にしても良い片付け、しない方が良い片付けの内容をご紹介します。
1. 相続放棄するなら家の片付けをしてはいけない?
結論として、家の片付けの内容によっては、相続放棄ができなくなる可能性があります。まずは、相続放棄の基本を確認しつつ、安易に家の片付けをしない方が良い理由を理解しましょう。
(1)相続放棄の基本を整理
相続放棄とは、相続人が、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否することです。相続放棄をすると、マイナスの財産(借金やローンなど)はもちろん、プラスの財産(預貯金や不動産など)も含めた一切の相続財産を引き継ぐことができません。
相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書等の書類を提出する必要があります。
また、相続放棄には次のようなルールがあることを覚えておきましょう。
- 相続放棄は他の相続人の同意なしに単独で行うことができる。
- 被相続人の生前に相続放棄をすることはできない。
- 特定の財産だけ選んで相続放棄をすることはできない。
相続放棄の手続きや注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
(2)相続財産を「処分」すると相続放棄ができなくなる
相続人であれば、基本的に誰でもできる「相続放棄」ですが、一定の行為をすると相続放棄ができなくなったり、すでにした相続放棄が無効になったりすることがあります。
特に、相続財産の「処分」や「隠匿」に該当する行為には注意が必要です。たとえ意図せずこれらの行為をしたとしても、相続放棄ができなくなるなどのリスクがあります。
(法定単純承認)
民法921条1号、3号
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 (省略)
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法に定められたルールによれば、相続財産の「処分」や「隠匿」に該当する行為をした人は、「単純承認」をしたものとみなされます。
単純承認とは、「通常通り故人の権利義務を全て引き継ぎます」と認めることです。つまり、強制的に通常通り相続したものとして扱われてしまうのです。
そのため、被相続人に債務(借金・ローン・損害賠償債務など)がある場合にはそれも相続し、被相続人の代わりに支払っていかなければならないということになります。
(3)家の片付けは相続財産の処分に当たる可能性がある
では、本題である「家の片付け」はどうでしょうか。結論としては、具体的にどのような片付けを行うのかによって扱いが変わってきます。
相続財産の「処分」や「隠匿」に該当する片付けをしてしまえば、相続放棄ができなくなる可能性があります。
反対に、相続財産の「処分」や「隠匿」に該当しない片付けなのであれば、相続放棄に影響はありません。
2. しない方が良い家の片付けの具体例
「具体的に何をしてはいけないの?」とお思いの方も多いはずですので、まずは、しない方が良い「家の片付け」の具体例をご紹介します。
(1)家を売却・解体・リフォームする
被相続人が所有していた家そのものを売却する行為は、典型的な相続財産の処分です。また、家の解体やリフォームも相続財産の処分に該当する可能性が高いでしょう。
家の解体が許される例としては、相続放棄をした後に家の管理義務を負ってしまったケースで、放っておけば倒壊しそうな老朽化した家を管理義務の一環として解体するようなケースが考えられます。そのような事情がないのであれば、家の解体などはしないようにしましょう。
また、今にも崩れそうなブロック塀を補修する行為など、相続財産の価値を維持する行為は行っても問題ありません。
このような行為は「保存行為」(民法921条1号但し書)に該当するものであり、「処分」には当たらないと考えられるためです。
(2)賃貸借契約の解約や敷金の受け取り
被相続人が賃貸の家に住んでいた場合には、被相続人の死亡後、管理会社や大家さんから賃貸借契約の解約を求められることがあるでしょう。
そのような場合、まずは管理会社や大家さんに対して相続放棄を予定しているため手をつけられないことを伝えましょう。
その上で、相続放棄をする予定がない他の相続人がいるのであれば、その相続人に解約をしてもらいます。
全員が相続放棄をして他に相続人がいないケースなら、貸主の側から一方的に解約してもらうのも一つの解決策です。
また、被相続人が賃貸借契約時に敷金を支払っていることがあります。賃貸借契約の終了に伴い、管理会社や大家さんから敷金を受け取るように言われることがあるかもしれません。
しかし、この敷金は被相続人の財産ですので、受け取ってはいけません。受け取ってしまうと、相続財産を処分したものとして、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
(3)腕時計・衣服・バッグなど高価な品の形見分け
形見分け(かたみわけ)とは、故人が所有していた物を親族や親交のあった人に贈ることです。思い出を分かち合うために行われる風習として、現在も広く一般的に行われています。
被相続人が残した遺品を整理する中で、一定の価値のある腕時計・衣服・バッグ・貴金属・宝飾品などが出てくることもあるでしょう。それらの物品を、「形見分け」などという名目で譲り受けたり、誰かにあげたりしてしまうと、相続財産の「処分」や「隠匿」に該当してしまいます。
実際に、そのような行為が相続財産の「処分」に当たるとして、単純承認が認められてしまった裁判例も存在します。
和服15枚、洋服8着、ハンドバッグ4点、指輪2個を相続人の一人に引き渡した行為が「処分」に当たるとして、単純承認とみなされた事例
(松山簡裁昭和52年4月25日判決)
(4)家具・家電などの売却や処分
故人の家を片付けようとしたとき、家具・家電などの大きなものの処分に困ることも多いと思います。だからといって、これらの物品を売却したり捨てたりしてしまうと、相続財産の「処分」等に該当してしまう可能性があります。
なお、家の片付けに伴う遺品の売却や廃棄が、相続財産の「処分」や「隠匿」に当たるかどうかは、その遺品に経済的価値があるかどうかが重要なポイントとなります。
遺品に経済的価値がある場合には、譲り受けたり、捨てたり、売却したりしてはいけません。
自分が利益を得ようと意図している場合はもちろんのこと、意図せず捨ててしまったり、他人に譲ったりしてしまった場合でも、相続を認めたものとみなされる可能性があります。
(5)相続財産から家賃や公共料金を支払う
家の片付けを進める中で、家賃、電気・ガスなどの光熱費、水道料金、通信費などの未払い金が発覚することがあります。
未払いの状態がついつい気になってしまい、被相続人が遺した現金や預貯金で支払ってしまう方がいますが、これもやめておいた方が良いでしょう。被相続人のお金を支払いに充てる行為は、相続財産の処分に該当します。
相続放棄をするのであれば、被相続人が負っていたこれらの債務について返済する必要はありません。
(6)車・バイクなどの売却や廃車処分
被相続人が遺した車やバイクも片付けの対象に入ってくるでしょう。
車やバイクについては、まずは車検証等を見て、現在の所有者が誰であるかをしっかりと確認してください。
ローンの支払い途中の車などは、所有権がローン会社やディーラーに残っていることも少なくありません。当然ながら、そのようなものを勝手に売却したり廃車にしたりしてはいけません。
仮に、車やバイクの所有者が被相続人であったとしても、車やバイクに経済的価値があるにも関わらず売却や廃車処分をしてしまえば、相続財産の「処分」や「隠匿」に該当する可能性があります。
3. 相続放棄に影響を与えない家の片付けの具体例
次に、相続放棄に影響を与えない家の片付けの具体例を見ていきます。これらの行為をしたとしても、相続放棄ができなくなったり、すでにした相続放棄が無効になってしまう心配はないといって良いでしょう。
(1)明らかなゴミを捨てる
被相続人の家に残された空き缶やペットボトル、食品や生活用品のパッケージなど、明らかなゴミであれば捨ててしまって構いません。
放っておいたら短期間で腐ってしまうような食品なども廃棄して良いでしょう。何も手をつけず放っておいたことで、悪臭を放ったり虫が湧いてしまったりすれば、近隣トラブルにも発展しかねません。
また、物の場所を移動して部屋の整理をしたり、ほこりや汚れをきれいにするための掃除をしたりしても問題ありません。
(2)経済的価値のないものをもらう
遺品であっても、一般的に経済的価値がないものであれば、譲り受けでも問題ありません。
例えば、形見分けとして、思い出のアルバムや写真、着古した衣類などを譲り受けたり、誰かにあげたりする行為は許容範囲であると考えられます。
ただし、一見古いものであっても、ヴィンテージ品として価値のある服や靴、腕時計などもありますので、判断は慎重にしてください。
(3)孤独死などにおける特殊清掃
いわゆる孤独死が発生してご遺体の発見が遅れてしまったケースなどにおいては、匂いや汚れの除去が通常の清掃では対処しきれないことがあります。
そのようなときは、専門的な知識や技術を持つ特殊清掃業者に清掃を依頼するのが一般的です。特殊清掃をしたからといって相続放棄ができなることは基本的にないと言って良いでしょう。
ただし、特殊清掃には5万円〜数十万円の費用がかかるのが一般的です。この費用を故人の預貯金などから支払った場合には、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。
社会通念に照らして許容されることもあるとは思いますが、相続放棄ができなくなるリスクを最小限に抑えたいのであれば、費用は貸主側の負担あるいは相続人の負担とした方が良いでしょう。
4. 全員が相続放棄したときはどうする?
家の片付けに関連して、「相続人全員が相続放棄したらどうするの?」という疑問が生じる方もいらっしゃるでしょう。ここからは、法定相続人の全員が相続放棄をしてしまった場合の処理について解説します。
(1)相続放棄後も管理義務を負う可能性【改正民法:2023年4月〜】
前提として、相続放棄をする時に相続財産を「現に占有」していた人は、相続放棄をした後も相続財産の管理義務(保存義務)を負うことがあります。
例えば、被相続人と同居していた人などは、家そのものや家具家財等に関して「現に占有」していた人に該当するでしょう。
管理義務(保存義務)とは、財産を滅失させたり損傷させたりしてはならないという意味です。解釈によっては、現状を維持すること(建物であれば適宜修繕等を行うこと)までも義務として含まれているとする考え方もできます。
家の中に残された物品のように持ち運べる物であれば、それらをまとめて特定の場所に保管しておくなどの管理が求められるでしょう。
これらの管理義務を負う期間について、民法は次のとおり定めています。
- 他に相続人がいる場合には、その相続人に財産を引き渡すまで
- 他に相続人がいない場合には、相続財産清算人に財産を引き渡すまで
全員が相続放棄をしてしまって他に相続人がいないときは、後者の「相続財産清算人に財産を引き渡すまで」となります。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法940条
(2)相続財産清算人の選任の申立て
法定相続人の全員が相続放棄をして、相続財産を受け継ぐ相続人がいなくなってしまったら、相続財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになります。
ただし、放っておけば自動的に国が相続財産を持っていって処理してくれるわけではなく、国庫に帰属させるまでの法的手続きが存在します。具体的には、「相続財産清算人の選任の申立て」をするなどの手続きを踏む必要があります。
家庭裁判所に選任された相続財産清算人は、亡くなった方の債権者に対して債務の支払いをするなどして清算をし、清算後に残った財産を国庫に帰属させます。
このように、相続人全員が相続放棄をしたあとは相続財産清算人が手続きを進めることになりますので、家庭裁判所に選任を申し立てるようにしましょう。
管理義務を負っていた人は、相続財産を相続財産清算人に引き渡せば、その時点で管理責任から解放されます。
相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった後の流れなどについては、下記の記事で詳しく解説しています。
5. 相続放棄したい人が家の片付けをするときの注意点
(1)家の片付けを求められても安易に応じない
被相続人が賃貸の家に住んでいた場合には、貸主側から「早く部屋の片付けをして部屋を明け渡してほしい」などと言われることもあるでしょう。
それをプレッシャーに感じて安易に家の片付けをすると、相続財産の「処分」や「隠匿」に該当してしまうリスクがあることは、これまで説明したとおりです。
基本的には、相続放棄をするのであれば、このような要求に応じる義務はありませんが、現実問題として放置できないこともあるかもしれません。
その場合は、少しでも価値のありそうな家財道具をあなたの自宅などに移動させ、ひとまず保管するというのもひとつの方法です。
並行して相続放棄の手続きを進め、相続財産清算人が選任され次第、すみやかに家財道具などを相続財産清算人に引き渡せば問題ないでしょう。
(2)トランクルームなどの活用も検討
自宅のスペース等の問題で、被相続人の遺品を自宅に保管できない方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、トランクルームなどを借りて保管するのも一つの手です。
(3)故人の預貯金には手をつけない
相続放棄をするのであれば、故人の預貯金には基本的に手をつけないようにしましょう。それだけでも、うっかりと相続財産の処分等をしてしまうリスクを軽減できるはずです。
被相続人の葬儀費用に充てざるを得ないなど、特別な理由があって預貯金を引き出す場合には、葬儀費用の領収書等を必ず残しておくようにしてください。
正当な理由で預金を引き出したことをいつでも第三者に証明できる状態にしておかないと、「本当に葬儀代として支出したのか?」という疑いが生じてしまい、最悪の場合相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
6. まとめ|困ったら弁護士に相談を
この記事では、相続放棄をしたい人が家の片付けをしても良いのかという点について解説しました。
確実に相続放棄をしたいのであれば、漠然と「家の片付けはしても良いのか」と考えるのではなく、もう少し具体的に何をしたいのか、何をしようとしているのかをはっきりさせ、その行為が相続財産の処分や隠匿に当たらないかを検討する必要があります。
相続放棄への影響を十分に考えず安易に行動してしまうと、最悪の場合相続放棄ができなくなったり、すでに受理されている相続放棄が無効になってしまったりするリスクがあります。
ご自身で判断するのが不安な方は、相続放棄の手続きに詳しい弁護士に相談しましょう。